アンケートと調査の違いを徹底解説|定義・目的・使い分けのポイント

こんにちは。デジタルマーケティングカンパニーのトウガサです。
情報収集や分析に携わるビジネスパーソン、研究者、学生の皆様にとって、アンケートと調査は重要なツールです。しかし、これらの言葉が混同して使われることも少なくありません。本記事では、アンケートと調査の定義、目的、適切な使い分け、効果的な実施方法、そしてデータ分析の手法について、リサーチ活動に役立つ体系的かつ実践的な情報を提供します。
アンケートと調査の基本的な違い
アンケートと調査は、どちらも情報収集の手段ですが、その意味合いや範囲には明確な違いがあります。これらを理解することは、適切なリサーチ活動を行う上で重要です。
アンケートとは
アンケート(フランス語の「enquete」に由来)とは、特定の情報や意見を収集するために、対象者に対して質問を行う調査方法の一種です。通常、すでに一定の知見を持つ専門家やユーザーを対象に実施されます。
具体的には、自記式調査票を配布して回答を求めるのが一般的な方法ですが、電話、はがき、Webを介したものも広く用いられています。日本においては、多数のユーザーに定型の質問をする調査が多く行われる傾向があります。アンケートは、データ収集のための質問リストという意味合いが強く、定量的な情報を効率的に集めることを目的としたリサーチ手法として位置づけられます。

調査とは
調査とは、ある事柄の実態や動向、事実関係などを明確にするために、様々な手段を用いて情報を集める広範な活動を指します。英語では「survey」や「research」と表現され、企業や公的機関、学術研究など幅広い分野で実施される重要な情報収集の手段として機能します。
調査の対象は、個人の意識や行動だけでなく、社会全体の傾向や自然現象、歴史的事実など多岐にわたります。アンケートは、この「調査」という大きな枠組みの中の一つの情報収集方法、つまりリサーチ手法として位置づけられます。

調査研究とは
調査研究とは、特定の事象や現象を分析する目的のために、観察、検査、アンケート、面接などの手法を用いて資料を収集し、分析する活動を指します。これは、人為的な条件を設定しない点が実験研究と異なります。
調査研究は、解決すべき問題の正確な性質を明らかにするための予備調査や、新しい知識や理論を生み出すための長期的な探究活動としても位置づけられ、既存の知見に基づいたデータや情報の収集と記録を目的とします。具体的には、先行研究を調べる文献調査や、対象者の意識・行動を測定する質問紙調査、インタビュー調査などが含まれます。

アンケートと調査の目的
アンケートと調査はそれぞれ異なる目的を持って実施されます。これらの目的を明確にすることで効果的な情報収集と分析が可能となります。
アンケートの目的
アンケートの主な目的は、対象者の意見、経験、好みなどを効率的に収集することです。これにより、企業や組織は製品開発、サービス改善、マーケティング戦略の立案などに役立つ貴重な情報を得ることができます。例えば、新製品の開発前に顧客の評価や改善点を把握したり、顧客満足度を高めるための具体的な要望を収集したりする場合にアンケートが活用されます。
アンケートの目的を明確にすることは、質問の設計、回答方法の選択、対象者の選定といった作成プロセスを円滑にし、回答者の協力を得やすくするだけでなく、集計・分析を効率的に行うためにも不可欠です。

調査の目的
調査の目的は、特定の事象の実態や動向を解明し、現状を正確に把握することにあります。これには、市場や顧客のニーズを把握し、ビジネスにおける意思決定をサポートする役割があります。例えば、新しいプロジェクトを立ち上げる前の実現可能性やリスク評価、あるいは政策の策定や改善に必要な情報を収集するために調査が実施されます。
調査は、課題の把握、実態の詳細な把握、課題の原因分析、事業効果の測定、改善策の効果検証など、PDCAサイクルの各段階において重要な役割を果たします。
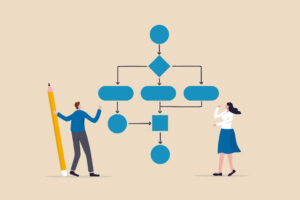
アンケートと調査の種類

アンケートと調査にはそれぞれ目的に応じた多様な種類が存在します。
アンケートの主な種類
アンケートは大きく「定量調査」と「定性調査」の2種類に分けられます。定量調査では数値化できるデータを収集し、全体の傾向や割合を把握するのに適しています。一方、定性調査は数値では表せない意見や感情、動機などを深く掘り下げて理解することを目的とします。
定量調査のアンケートとしては、市場調査、顧客満足度調査、商品開発アンケートなどがあり、特定の期間内に質問をして回答を求め、データを集めます。
定性調査のアンケートは、自由記述やオープンエンド形式の質問が多く、回答者の詳細な意見や感情を把握するのに役立ちます。アンケートの種類は、目的によって使い分けることが重要です。

アンケートの質問形式
アンケートの質問形式には、大きく分けて「選択形式」と「自由記入形式」があります。選択形式は、回答者が提示された選択肢の中から回答を選ぶ形式で、単一回答、複数回答、スケール形式(5段階評価など)などがあります。
単一回答は明確な意思を把握するのに適しており、複数回答は幅広い選択肢から傾向を掴むのに役立ちます。スケール形式は、満足度や重要度などの度合いを定量的に把握する際に有効です。
自由記入形式は、回答者が自由に意見や感想を記述する形式で、予想外の意見や詳細な情報を得られる可能性があります。ただし、自由記入は回答者の負担が大きく、分析に時間がかかるため、重要な部分に絞って利用することが推奨されます。

調査の主な種類
調査には多岐にわたる種類があり、リサーチの目的に応じて適切な手法が選択されます。主な調査の種類としては、世論調査、意識調査、国勢調査、市場調査、学術調査などが挙げられます。
世論調査や意識調査は、個人の思考や感情を探り、社会的な意見を把握するために行われます。国勢調査は、国民生活の実態や人口動向を明らかにするための大規模な調査です。
市場調査は、企業が製品開発やマーケティング戦略の立案のために、市場の現状や顧客ニーズを把握することを目的とします。
学術調査は、特定の仮説を検証したり、新しい知見を発見したりするために、系統的なリサーチ計画に基づいて実施されます。
これらの調査は、訪問聞き取り、会場での面接、電話、郵送、インターネットなど、多様な方法で実施されます。
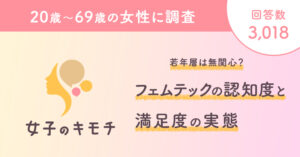
アンケート作成と実施のポイント
効果的なアンケートを作成し、正確なデータを収集するためには、いくつかの重要なポイントがあります。これらを理解し、適切な作り方でアンケートを実施することで、調査の質を高めることができます。
アンケート作成のステップ
アンケートを作成する際は、以下のステップを踏むことが重要です。
まず、調査の目的を明確にします。これは、どのような情報を得たいのかを具体的に設定する最も重要なステップです。目的が不明確だと、適切な設問を設定できず、得られたデータも活用しにくくなります。
次に、調査対象を決定し、必要なサンプル数を算出します。性別、年齢、職業、既存顧客か見込み顧客かなど、目的と内容に応じた適切なターゲットに絞り込むことが重要です。
その後、質問内容、回答形式、質問文、選択肢を具体的に設計し、調査票を作成します。回答方法(紙、Webなど)を決めてアンケートフォームを組み立て、最後に内容を最終確認します。
これらのステップを順序立てて行うことで、質の高いアンケートの作り方が実現できます。

設問作成の工夫
設問を作成する際には、回答者がスムーズかつ正確に回答できるよう、いくつかの工夫が必要です。まず、質問文は簡潔で分かりやすい言葉遣いを心がけ、誰にでも理解できる表現を使用します。専門用語や業界用語は避け、もし使用する場合は簡単な説明を加えるなど配慮しましょう。質問の意図が明確でないと、回答者が迷ったり、誤った解釈をして回答してしまったりする可能性があります。
また、一つの設問で複数の内容を問う「ダブルバーレル質問」は避け、一問一答形式で質問を構成することが重要です。質問の順序も重要で、導入部分には回答しやすい簡単な質問を配置し、個人情報に関する質問はアンケートの最後に配置するなど、回答者の負担を考慮した流れにするのが効果的です。回答形式についても、単一回答、複数回答、自由記述などを適切に使い分け、回答者の負担を軽減しつつ、目的に合ったデータを収集できるように工夫します。

回答率を高めるための留意点
アンケートの回答率を高めるためには、回答者の負担を減らし、協力意欲を引き出す工夫が不可欠です。まず、アンケートの趣旨と目的を明確に伝え、回答がどのように活用されるかを具体的に示すことで、回答者は協力する意義を感じやすくなります。設問数を必要最低限に絞り、回答にかかる時間の目安を冒頭に提示することで、回答へのハードルを下げられます。
質問形式は、思考を要する自由記述形式を減らし、選択式を中心にすることで、回答者の負担を軽減できます。また、回答者にとって魅力的な謝礼やインセンティブを用意することも、回答率向上に効果的です。アンケートの配布チャネルも重要で、ターゲット層に合わせたWebアンケート、紙媒体、電話など適切な方法を選択することで、より多くの回答を得られる可能性があります。これらの留意点を踏まえることで、回答率の向上と、信頼性の高いデータ収集が期待できます。

アンケートの実施形式
アンケートの実施形式は、目的やターゲット層によって多様な選択肢があります。主な形式としては、Webアンケート、紙媒体、電話、郵送などがあります。Webアンケートは、インターネットの普及に伴い近年主流となっており、効率的なデータ収集と集計が可能です。回答者はパソコンやスマートフォンから手軽に回答でき、顧客データと紐付けて分析できるメリットがあります。
しかし、インターネットに不慣れな層には適さない場合があります。
紙媒体のアンケートは、高齢者層やインターネット環境にない対象者から回答を集める際に有効です。
電話調査は、口頭で詳細な情報を引き出せる利点がありますが、時間とコストがかかる傾向があります。郵送調査は、広範囲の対象者にアプローチできますが、回収までに時間がかかります。
適切な実施形式を選ぶことで、回答率の向上と、質の高いデータ収集に繋がります。

アンケートデータの分析とまとめ方

アンケートを実施して得られたデータは適切に分析しその結果を分かりやすくまとめることでビジネスの意思決定や課題解決に役立てることができますアンケート調査の分析は得られたデータを最大限に活用するために不可欠なプロセスです
基本的なデータ集計方法
アンケート調査の分析に入る前に、まず回答データ全体を整理し、数値にまとめる「集計」作業が必要です。基本的な集計方法には、「単純集計(GT)」と「クロス集計」の2種類があります。
単純集計は、各設問に対して、どの選択肢が何人に選ばれたかを合計し、割合などを算出する最も基本的な方法で、アンケート結果の全体的な傾向を素早く把握するのに役立ちます。例えば、「商品の満足度」について「満足」「どちらとも言えない」「不満」の割合を出すことで、全体の満足度傾向が分かります。
クロス集計は、単純集計の結果をさらに別の設問(性別、年代など)と掛け合わせ、より詳細に分析する手法です。特定の層にどのような傾向があるかを深掘りでき、例えば「女性の満足度は高いが、男性の満足度は低い」といったインサイトを発見できます。これらの基本的なアンケート調査の分析方法を理解し、適切に活用することが、より深い分析への第一歩となります。

代表的なデータ分析手法
アンケート調査の分析には、基本的な集計方法に加えて、より深い洞察を得るための多様な分析手法があります。代表的なものとしては、クラスター分析、アソシエーション分析、主成分分析、決定木分析、時系列分析などが挙げられます。
クラスター分析は、異なる特性を持つデータの集合から、似た特性を持つデータを集団(クラスター)にまとめ、対象を分類する手法で、顧客セグメンテーションや商品のポジショニング分析などに活用されます。
アソシエーション分析は、データ間の関連性を分析し、「ある事象が発生した場合、結果はこうなるだろう」といった法則を導き出す手法です。例えば、「商品Aを購入した人は、商品Bも購入することが多い」といった傾向を分析し、商品の陳列や品揃えの検討に役立てます。
決定木分析は、データを階層的に分類し、意思決定プロセスを視覚化するツリー構造を作成する手法で、ターゲット層の特定や顧客満足度に影響を与える要因の分析などに活用されます。
これらのアンケート調査の分析手法は、目的に合わせて適切に選択し、単なる数値の羅列ではなく、意味のある洞察を引き出すことが重要です。

有意性の考慮
アンケートデータの分析において、得られた結果が偶然によるものではなく、統計的に意味のあるものであるか(有意性)を考慮することは非常に重要です。特に、収集したデータが一部のサンプルに偏っている場合や、サンプル数が少なすぎる場合には、その分析結果が全体を正確に反映しているとは限りません。例えば、アンケートの回答率が低い場合、そのデータは有用な情報を収集できていない可能性があり、信頼できるサンプルサイズと人口統計学的範囲が必要となります。
統計的有意性を確認するためには、仮説検定などの統計手法を用いることが一般的です。これにより、分析結果が単なる偶然の産物ではないことを客観的に示すことが可能となります。また、相関関係と因果関係を混同しないよう注意することも、分析の質を高める上で重要なポイントです。有意性を考慮することで、アンケート調査の分析結果に基づいて、より信頼性の高い意思決定や施策立案を行うことができるでしょう。

まとめ|目的に合った「調査設計 × アンケート運用」をプロが伴走します
本記事で整理したとおり、調査=枠組み/アンケート=手法です。成果に直結させるには、目的から逆算した手法選定・サンプル設計・設問設計・実査・分析・示唆出しまでを一貫して設計することが鍵になります。株式会社オノフでは、ビジネス/公共/学術まで幅広い領域で、定量・定性・混合型を最適に組み合わせて支援します。
- 調査設計:目的・仮説の言語化、手法の使い分け(定量/定性/混合)、サンプル設計・母集団定義
- アンケート設計:設問・選択肢・順序設計、バイアス/ダブルバーレル回避、プレテスト
- 実査運用:Web/郵送/電話など最適チャネル、回答率向上施策、個人情報保護への配慮
- 分析・可視化:単純/クロス集計、統計検定・有意差、クラスター/決定木等の深掘り、ダッシュボード
- 示唆とアクション:意思決定に直結するインサイト整理、次アクション提案・検証設計
「既存アンケートの診断だけ」「設問のリライト」「分析とレポートだけ」などスポット依頼も歓迎です。課題や目的を一言で構いません、まずはご相談ください。
