アンケート調査 満足度測定の項目例と作り方|集計・分析方法も解説

こんにちは。デジタルマーケティングカンパニーのトウガサです。
企業が商品やサービスを提供する上で、顧客がどれだけ満足しているかを把握することは、事業の成長に不可欠です。顧客満足度調査は、顧客の生の声を聞き、自社の強みや弱みを客観的に理解するための有効な手段です。本記事では、顧客満足度調査の具体的な実施方法、アンケート項目の設計、結果の集計・分析、そしてその後の改善策への繋げ方まで、実践的な情報を詳しく解説します。
顧客満足度調査の概要
顧客満足度調査(CS調査)は、自社の商品やサービスを利用した顧客の満足度や期待度を把握し、数値化して分析する調査手法です。この調査によって得られた情報は、商品開発やサービス改善、さらにはマーケティング戦略の策定に活用されます。顧客満足度をデータとして可視化し、具体的な改善策の立案や経営戦略に役立てることが目的です。
顧客満足度調査を行う目的
顧客満足度調査を行う目的は多岐にわたりますが、主に既存の商品やサービスの改善、競合他社との比較、商品やサービスの信頼性向上にあります。顧客の本音を把握することで、提供しているサービスが顧客の期待に応えられているか、または改善すべき点があるかを明確にすることが可能です。
例えば、新商品リリース後に顧客満足度を調べることで、改善点を特定し、次のアクションプランに活かすことができます。また、競合他社と比較して自社の強みや弱みを客観的に把握し、市場における自社の立ち位置を見直すことにも繋がります。さらに、顧客満足度が高いことを公表すれば、新規顧客の獲得や売上拡大に繋がり、企業の信頼性向上にも貢献します。

顧客満足度の主な指標
顧客満足度を測定し、客観的に評価するためには、適切な指標を用いることが重要です。指標には測定方法や分析の視点が異なるため、自社の目的に合った指標を選択する必要があります。主な指標として、NPS(ネット・プロモーター・スコア)、CSAT(顧客満足度スコア)、JCSI(日本版顧客満足度指数)が挙げられます。これらの指標を継続的にモニタリングすることで、顧客満足度の動きや傾向を把握し、ビジネスの成長に役立てることができます。

NPS®(ネット・プロモーター・スコア)
NPS(ネット・プロモーター・スコア)は、顧客ロイヤルティを数値化する指標で、
「この商品やサービスを友人や同僚に勧める可能性はどのくらいありますか?」
という質問に対し、0から10の11段階で回答してもらい算出します。
回答者は「推奨者(9〜10点)」、「中立者(7〜8点)」、「批判者(0〜6点)」に分類され、
推奨者の割合から批判者の割合を引いた数値がNPSスコアとなります。
この数値が高いほど、顧客ロイヤルティが高いことを示しており、シンプルさと顧客ロイヤルティとの相関性の高さから、多くの企業で顧客満足度を測る指標として採用されています。NPSは、顧客の行動意向を直接的に問うため、企業の成長性とも高い相関があると考えられています。
CSAT(顧客満足度スコア)
CSAT(顧客満足度スコア)は「Customer Satisfaction Score」の略で、自社の商品やサービスに対する顧客満足度を測る指標です。
具体的には、自社製品やサービスを利用した顧客に対し、
「全体的な満足度はどれくらいですか」といった質問を投げかけます。
回答は「非常に不満」「不満」「どちらでもない」「満足」「非常に満足」といった5段階のリッカート尺度で答えてもらうことが一般的です。
CSATは、これらの回答のうち「満足」と「非常に満足」を選んだ顧客数の割合を算出し、100%に近いほど良いとされています。この指標は、特定の商品やサービスに対する短期的な満足度を把握するのに適しており、視覚的に把握しやすい形で顧客満足度を測定できます。
JCSI(日本版顧客満足度指数)
JCSI(日本版顧客満足度指数)は、サービス産業生産性協議会が主体となって実施している日本最大級の顧客満足度調査で、「日本版顧客満足度指数」と呼ばれます。これはCSI(CustomerSatisfactionIndex)を日本向けにカスタマイズした指標であり、顧客期待、顧客不満、知覚品質、知覚価値、顧客忠実度、推奨意向の6項目に関して質問を行い、0から100点で評価してもらうことで顧客満足度を算出します。
JCSIは、多角的な視点から顧客満足度を捉えることができるため、より詳細な分析に役立ちます。これにより、企業は市場における自社の立ち位置や、商品・サービスの強みと弱みを客観的に把握することが可能です。
顧客満足度調査のアンケート項目と設問例
顧客満足度調査のアンケート項目は、調査目的によって多岐にわたりますが、回答者の属性から商品・サービスの利用状況、満足度、継続利用意向、推奨意向、そして自由回答形式の意見や要望まで、多角的な視点から構成することが重要です。適切な設問を設定することで、顧客の本音を捉え、具体的な改善策に繋がる有益な情報を得ることが可能になります。アンケートはシンプルで集計しやすい設問を心がけ、回答者の負担を軽減することも回答率向上のポイントです。
回答者の属性に関する項目
回答者の属性に関する項目は、顧客満足度調査の分析において非常に重要です。性別、年代、居住地、職業、世帯年収といったデモグラフィック情報だけでなく、利用頻度や購入チャネルなどの行動履歴に関する情報も収集することで、回答全体の傾向を把握しやすくなります。
例えば、「性別」や「年代」を問うことで、どのような層が自社の商品やサービスに満足しているのか、あるいは不満を感じているのかを特定できます。これにより、特定の顧客層に特化した改善策を検討したり、新たなターゲット層の開拓に繋げたりすることが可能になります。
また、「居住地」や「職業」などの項目は、地域性やライフスタイルが顧客満足度に与える影響を分析する際にも役立ちます。これらの属性情報を収集することで、単なる満足度の数値だけでなく、その背景にある顧客像をより深く理解し、パーソナライズされたマーケティング戦略やサービス改善に繋げられるでしょう。アンケートの設問設計時には、これらの属性項目を網羅し、回答者が抵抗なく答えられるような表現を心がけることが大切です。

商品・サービスを知ったきっかけ
商品・サービスを知ったきっかけに関する設問は、顧客の認知経路を把握し、マーケティング施策の効果を測定する上で非常に重要です。
例えば、
「当社の商品・サービスをどこで知りましたか?」といった質問に対し、
「インターネット検索(Google/Yahooなど)」「SNS広告(Instagram/X/Facebookなど)」
「知人・家族からの紹介」「テレビCM・新聞・雑誌」「店舗で偶然見つけた」「その他(自由記入)」などの選択肢を設けることで、多様な認知経路を網羅できます。これにより、どのチャネルからの流入が顧客獲得に最も貢献しているのか、あるいは改善の余地があるのかを特定できます。
例えば、特定のSNS広告からの流入が多い場合は、その広告の内容やターゲット設定が適切であると判断でき、さらに強化する施策を検討できます。逆に、特定の広告媒体からの流入が少ない場合は、その媒体でのプロモーション戦略を見直すきっかけとなるでしょう。また、「その他」の自由記入欄を設けることで、想定外の認知経路や具体的なエピソードを収集でき、新たなマーケティングのヒントを得られる可能性もあります。これらの情報は、今後の広告戦略やプロモーション活動の最適化に直結し、効率的な顧客獲得に繋がります。

商品・サービスの利用・購入状況
商品サービスの利用購入状況に関する項目は、顧客が自社の商品やサービスをどのように利用しているかを具体的に把握するために不可欠です。
例えば、
「当社の(商品サービス)をどれくらいの頻度で利用していますか?」や
「今回購入した商品サービスの種類を教えてください(複数選択可)」といった質問が挙げられます。
これらの設問によって、顧客の利用頻度や購入履歴、購入した商品の種類などを詳細に把握できます。例えば、特定の機能が頻繁に利用されていることが分かれば、その機能のさらなる強化や関連サービスの開発に繋げられます。また、購入頻度の高い顧客層を特定することで、リピーター獲得のための具体的な施策を検討できるでしょう。単一回答だけでなく、複数回答を可能にすることで、顧客の多様な利用状況や購入パターンをより正確に捉えることが可能となります。
さらに、過去の購入履歴や利用状況を把握している顧客に対しては、アンケートの設問を最適化し、よりパーソナルな質問をすることで、深いインサイトを得ることも考えられます。これらの情報は、商品サービスの改善だけでなく、顧客ごとのニーズに合わせた個別のアプローチを検討する上でも重要なデータとなります。

商品・サービス選定の重視点
商品・サービス選定の重視点に関する設問は、顧客が商品やサービスを選ぶ際に何を最も重要視しているかを明らかにするために不可欠です。
例えば、
「商品・サービスを選ぶ際に重視する点について、あてはまるものをすべてお選びください」
といった質問に対し、品質、価格、機能、デザイン、ブランドイメージ、サポート体制、口コミ・評判、利便性、アフターサービスなど、具体的な選択肢を複数提示します。
これにより、顧客がどのような要素に価値を感じているのかを把握し、自社の商品やサービスが顧客のニーズに合致しているかを評価できます。例えば、顧客が価格を最も重視しているにもかかわらず、自社が品質に重きを置いている場合、マーケティング戦略や商品開発の方向性を再検討する必要があるかもしれません。また、顧客が重視する点が自社の強みと合致していれば、その強みをさらにアピールするプロモーション戦略を強化できます。これらの情報は、競合他社との差別化を図る上でも重要な示唆を与え、商品開発やサービス改善の優先順位を決定する際の根拠となります。
さらに、「その他」の自由記入欄を設けることで、選択肢では網羅しきれない顧客独自の重視点を発見できる可能性もあります。
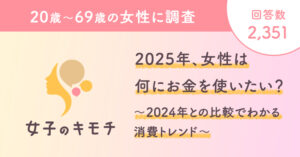
総合的な満足度と項目別の満足度
総合的な満足度と項目別の満足度を問う設問は、顧客満足度の全体像を把握しつつ、具体的な改善点を特定するために不可欠です。
まず、総合的な顧客満足度を尋ねる設問では、
「当社の○○(商品・サービス)全体について、どの程度満足していますか?」といった形で質問します。回答形式としては、非常に満足から非常に不満までを網羅する7段階評価が、顧客の気持ちをより詳細に捉える上で効果的です。
例えば、「非常に満足」「満足」「やや満足」「どちらでもない」「やや不満」「不満」「非常に不満」といった尺度を用いることが考えられます。これにより、顧客満足度の全体的な傾向を把握できます。
次に、項目別の満足度では、商品・サービスの品質、機能、価格、使いやすさ、サポート体制、デザインなど、具体的な要素ごとに顧客満足度を評価してもらいます。例えば、「○○の品質について、どの程度満足していますか?」といった形で、各項目に対して同様の7段階評価を求めます。これにより、総合的な満足度が高い場合でも、特定の項目に不満があるといった隠れた課題を発見できます。例えば、総合満足度は高いものの、サポート体制への満足度が低いといった結果が出た場合、サポート体制の強化が顧客ロイヤルティ向上に繋がる可能性が高いと判断できます。これらの設問は、顧客満足度の具体的な要因を特定し、効果的な改善策を立案するための重要な基礎情報となります。

商品・サービスの継続利用意向
商品・サービスの継続利用意向に関する設問は、顧客ロイヤルティの高さや将来的な売上を予測するために重要な項目です。
具体的には、
「今後も○○(商品・サービス)を使い続けたいと思いますか?」や
「○○(商品・サービス)の利用を継続する可能性はどれくらいありますか?」
といった質問が挙げられます。
回答形式としては、「間違いなくそう思う」「そう思う」「どちらとも言えない」「そう思わない」「全くそう思わない」といった5段階評価を用いることが一般的です。
顧客が商品やサービスの利用を継続する意向があるかを知ることで、リピート率の予測や、顧客が離反するリスクの早期発見に繋がります。例えば、継続利用意向が低い顧客層が多い場合、その理由をさらに深掘りする追加調査や、離反防止のための施策を検討する必要があるでしょう。逆に、継続利用意向が高い顧客層を特定できれば、その層のニーズをさらに満たすことで、顧客ロイヤルティを強化し、長期的な関係を構築できます。この設問の結果は、顧客維持戦略やCRM(顧客関係管理)戦略を策定する上で不可欠な情報となり、顧客ライフタイムバリュー(LTV)の向上にも貢献します。

他者への推奨意向
他者への推奨意向に関する設問は、顧客ロイヤルティを測るNPS®(ネット・プロモーター・スコア)を算出するために不可欠な項目です。
具体的には、
「この商品やサービスを友人や同僚に勧める可能性はどのくらいありますか?」
といった質問が用いられます。回答は0点(全くそう思わない)から10点(非常にそう思う)までの11段階で評価してもらうのが一般的です。
この設問から得られるデータによって、回答者を「推奨者(9〜10点)」「中立者(7〜8点)」「批判者(0〜6点)」に分類し、NPS®を算出することで、顧客がどれだけ自社の商品やサービスに愛着や信頼を抱いているかを客観的に数値化できます。推奨者の割合が高いほど、ポジティブな口コミや紹介による新規顧客獲得の可能性が高く、企業の成長に繋がる良い兆候と判断できます。
逆に、批判者の割合が多い場合は、商品やサービスに深刻な問題がある可能性があり、早急な改善が必要となります。この設問は、単なる満足度だけでなく、顧客が能動的に他者に勧めるかどうかという行動意向を問うため、企業の収益性や持続的な成長と強い相関があるとされています。そのため、顧客満足度調査において非常に重要な指標の一つとして広く活用されています。

商品・サービスへの意見や要望(自由回答)
商品・サービスへの意見や要望を問う自由回答形式の設問は、選択式設問では得られない顧客の「本音」や「想定外の声」を収集するために非常に重要です。
例えば、
「この商品・サービスについて、ご意見やご要望がございましたらご自由にお書きください。また、前の設問で回答した評価の理由についてもお聞かせください。」
といった形で、具体的な意見や改善点を自由に記述してもらうことで、顧客が満足または不満を感じた具体的な理由や背景を深く掘り下げることができます。
顧客は、選択肢にない問題点や、個人的な使用体験に基づく細かな要望を持っている場合があるため、自由回答はそれらの「隠れたニーズ」や「ポジティブな不満」を顕在化させる貴重な機会となります。
例えば、
「〇〇の機能は素晴らしいが、操作が複雑で分かりづらいと感じた」
といった具体的な意見は、機能改善のヒントとなるでしょう。
また、「アフターサービスが迅速で丁寧だったので、安心して利用できた」といった肯定的な理由も、自社の強みを再認識し、さらに伸ばすための示唆を与えてくれます。
自由回答は集計・分析に手間がかかるという側面もありますが、テキストマイニングやアフターコーディングといった手法を活用することで、定性データを定量データに変換し、具体的な改善策に繋げることが可能です。これにより、顧客の期待と実際の体験とのギャップを明らかにし、より顧客視点に立った商品・サービス開発や改善に役立てることができます。

顧客満足度調査の実施方法

顧客満足度調査を効果的に実施するためには、明確な目的設定から始まり、適切な調査対象者の選定、具体的な調査方法の選択まで、一連の流れを計画的に進めることが重要です。漠然とした目的で調査を行うと、得られたデータが活用しにくく、効果的な施策に繋がらない可能性があります。また、オンライン調査や郵送調査、インタビュー調査など、多様な方法の中から、調査の目的や対象者に合わせて最適な方法を選ぶことが、顧客満足度を正確に把握するための鍵となります。
調査実施までの流れ
顧客満足度調査を実施するまでの流れは、計画段階から分析・改善まで複数のステップに分かれます。
まず、「目的の明確化」が最も重要です。何を知りたいのか、調査結果をどのように活用するのかを具体的に設定することで、適切な調査方法や質問内容を決められます。例えば、「既存商品の改善点を知りたい」のか、「新商品開発のためのニーズを探りたい」のかによって、対象者や設問は大きく変わってきます。
次に、「対象者の設定」を行います。調査目的に応じて、新規顧客、既存顧客、離反顧客など、どの顧客層に焦点を当てるかを決定します。例えば、離反顧客への調査では、サービスをやめた理由や不満だった点を深掘りすることで、課題解決のヒントを得られます。
続いて、「調査方法の決定」です。オンラインアンケート、郵送調査、電話調査、対面インタビューなど、収集したい情報の種類や予算、リソースを考慮して最適な方法を選びます。その後、「調査項目の作成」を行い、仮説に基づいた具体的な質問を設定します。この際、回答者の負担を考慮し、簡潔で分かりやすい質問を心がけることが大切です。
最後に、回答データの「集計・分析」を行い、レポートとしてまとめることで、具体的な改善策の立案や経営戦略に活用します。これらのプロセスを順序立てて進めることで、顧客満足度調査から最大限の価値を引き出すことが可能になります。

主な調査方法
顧客満足度調査には様々な方法が存在し、それぞれにメリットとデメリットがあります。主な調査方法としては、オンライン調査(ネットリサーチ)、郵送調査、電話調査、対面インタビューなどが挙げられます。オンライン調査はインターネットを通じてアンケートを実施する方法で、短期間で多くの回答を収集でき、コストも比較的抑えられる点が大きなメリットです。
特にWebアンケートシステムを活用すれば、設問作成から集計まで効率的に行えます。郵送調査はアンケート用紙を郵送し、返送してもらう方法で、インターネットを利用しない層にもアプローチできる点が強みですが、回収率が低くなる可能性や時間とコストがかかる点が課題です。電話調査はオペレーターが直接電話で質問し、回答を得る方法で、詳細な情報を聞き出せる可能性がありますが、回答者の負担が大きく、協力が得にくい場合があります。
対面インタビューは顧客と直接対話することで、表面的な回答だけでは分からない深層心理や感情、具体的な背景を詳細に引き出すことができる定性調査の手法です。少数の対象者から質の高い情報を得たい場合に有効ですが、時間やコストがかかる上に、分析には専門的なスキルが求められます。
調査目的や予算、ターゲット層に合わせて、これらの方法を単独で利用したり、複数組み合わせたりすることで、より多角的に顧客満足度を把握し、精度の高いデータを収集することが可能になります。例えば、定量的なデータはオンライン調査で大規模に収集し、深掘りしたい部分は対面インタビューで補完するといった活用方法が考えられます。

アンケートの集計と分析
アンケートで収集した生データは、そのままでは意味のある情報として活用できません。集計と分析のプロセスを経て、初めて顧客満足度の現状や課題、改善点が見えてきます。特に、単純集計やクロス集計といった基本的な集計方法に加え、平均値、中央値、最頻値といった代表値を用いることで、データの全体像や偏りを正確に把握し、より深い洞察を得ることが可能になります。
アンケート結果の集計
アンケート結果の集計は、収集した生データを意味のある形に整理する最初のステップです。最も基本的な集計方法として「単純集計」があります。これは、各質問項目に対してどの選択肢が何件回答されたか、その割合はどのくらいか(%)を算出する方法です。例えば、5段階評価の満足度に関する設問であれば、「非常に満足」が何件、「不満」が何件といった具合に、それぞれの回答数と割合を算出します。この単純集計を行うことで、アンケート結果の全体的な傾向を素早く把握でき、今後の分析の基礎となります。
また、数値で回答を得ている項目(例:利用頻度や購入金額)については、平均値を算出することも有効です。平均値は、全ての数値を合計し、そのデータの個数で割ることで算出されます。しかし、少数の極端な値(外れ値)が含まれる場合、平均値が全体の実態を正確に反映しないことがあるため、中央値(データを小さい順または大きい順に並べた際に中央に位置する値)や最頻値(最も多く出現する値)も併せて算出することが推奨されます。
これらの代表値を比較することで、データのばらつきや偏りを理解し、より正確な全体像を把握できるようになります。自由記述の回答については、テキストマイニングツールを活用したり、アフターコーディングによって類似する回答をグループ化したりすることで、定量的に集計し、分析に繋げることが可能です。

アンケート結果の分析
アンケート結果の分析は、集計されたデータから顧客満足度向上のための具体的な示唆やヒントを見つけ出す重要なプロセスです。集計されたデータを用いて、まずは単純集計で全体的な傾向を把握した後、より深い洞察を得るために「クロス集計」や「ポートフォリオ分析」といった手法を活用します。
クロス集計は、二つ以上の質問項目を掛け合わせて集計する方法で、特定の属性を持つ顧客層がどのような傾向を示すかを詳細に分析できます。例えば、「20代女性の顧客満足度」や「リピーターの商品に対する評価」など、特定のセグメントのニーズや不満点を明確にすることが可能です。これにより、顧客層ごとの課題や強みを特定し、ターゲットを絞った施策立案に役立てられます。
また、数値回答の項目では、平均値だけでなく、中央値や標準偏差も併せて確認することが重要です。平均値はデータの中心傾向を示しますが、極端な外れ値があると平均値が実態と乖離することがあります。中央値や標準偏差を確認することで、データのばらつきや偏りを把握し、より正確な分析が可能になります。さらに、ポートフォリオ分析は、顧客が重要だと考える項目と、それに対する実際の満足度を比較することで、改善すべき優先順位を明確にする分析手法です。例えば、重要度は高いにもかかわらず満足度が低い項目は、最優先で改善に取り組むべき点として特定できます。
自由記述の回答については、アフターコーディングやテキストマイニングによってキーワードの出現頻度や相関関係を分析することで、顧客の潜在的なニーズや具体的な不満点を抽出できます。これらの分析を通じて、顧客満足度を向上させるための具体的なアクションプランを策定し、継続的なPDCAサイクルへと繋げていくことが、アンケート調査を成功させる鍵となります。

顧客満足度調査実施のポイントと注意点

顧客満足度調査は、アンケートを実施してデータを収集するだけでなく、その目的を明確にし、質の高い設問を作成し、得られた結果を具体的な改善策に繋げることが不可欠です。調査を成功させるためには、回答者の負担を考慮した設問設計や、定期的な調査による経年変化の把握、そして調査結果を組織全体で共有し、行動に移すための仕組み作りが重要なポイントとなります。
アンケート設問作成時のポイント
アンケート設問を作成する際は、顧客満足度調査の目的を達成するために、いくつかの重要なポイントと注意点を押さえる必要があります。
まず、質問の意図を明確にし、回答者が迷わずに答えられるように簡潔で分かりやすい言葉を選ぶことが大切です。曖昧な表現や専門用語の使用は避け、誰にでも理解できる平易な言葉遣いを心がけましょう。
次に、回答者の負担を軽減するために、設問数を適切に調整することも重要です。質問が多すぎると回答途中で離脱してしまう可能性が高まります。質問の優先順位をつけ、本当に知りたい情報に絞り込むことが、回答率を向上させる鍵となります。
また、誘導的な質問や、回答者の感情を刺激するような質問は避けるべきです。例えば、「当社の素晴らしいサービスについてどう思いますか?」といった質問は、ポジティブな回答を促す誘導質問にあたるため、客観的な意見が得られません。回答形式については、単一回答、複数回答、自由記述など、質問内容や分析目的に合わせて最適な形式を選択しましょう。
特に、満足度に関する設問では、5段階や7段階といった評価尺度を用いることで、顧客の満足度を定量的に把握しやすくなります。さらに、自由記述欄を設けることで、選択肢では拾い上げられない顧客の具体的な意見や要望、想定外の声を収集できるため、積極的に取り入れることを推奨します。
これらのポイントを踏まえて設問を作成することで、質の高いデータを得ることができ、顧客満足度向上のための有効な示唆を引き出すことに繋がります。

調査結果を改善に繋げる方法
顧客満足度調査の実施後、その結果を単なるデータとして終わらせず、具体的な改善に繋げることが最も重要なステップです。
まず、調査結果を深く分析し、顧客満足度に影響を与えている要因を特定することが不可欠です。例えば、ポートフォリオ分析を用いて、顧客が「重要だと感じているが満足度が低い項目」を洗い出すことで、優先的に改善すべき点を明確にできます。
次に、特定された課題に対して具体的な改善策を立案し、実行に移します。この際、調査結果を現場の担当者を含め、関係部署全体で共有することが重要です。顧客満足度向上のための取り組みは、特定の部署だけでなく、企業全体で取り組むべき課題であるため、情報共有と連携を密にすることで、一貫性のある改善活動が可能になります。例えば、商品自体の改善だけでなく、カスタマーサポートの対応品質向上や、ウェブサイトのUI/UX改善、価格設定の見直しなど、多角的な視点から施策を検討します。
また、一度の調査で終わりではなく、定期的に顧客満足度調査を実施し、改善施策の効果を測定することも重要です。四半期ごとや年ごとなど、期間を決めて定点観測を行うことで、顧客満足度の推移を把握し、施策が顧客のニーズに合致しているか、期待通りの効果が出ているかを検証できます。もし期待通りの結果が得られない場合は、仮説を修正し、再度改善策を検討するといったPDCAサイクルを回すことが、継続的な顧客満足度向上に繋がります。
さらに、顧客からのフィードバックに真摯に対応し、改善への取り組みを顧客に伝えることで、顧客ロイヤルティの強化にも寄与します。
これらのステップを通じて、顧客満足度調査の結果を最大限に活用し、企業の持続的な成長を実現できるでしょう。

まとめ・お問い合わせ
顧客満足度(CS)調査は、設計の質と分析の深さが成果を左右します。株式会社オノフでは、目的整理・指標選定(NPS/CSAT/JCSI)から設問レビュー、サンプル設計・配信、回収・集計、テキストマイニング、ダッシュボード化、施策立案までを一気通貫でご支援。
BtoC/BtoB、店舗・EC・アプリ問わず、小規模スプリントから全国規模まで柔軟に対応します。現行アンケートの簡易診断やKPI設計のご相談だけでも歓迎です。
貴社のCS向上とLTV最大化に向けて、まずはお気軽にお問い合わせください。
