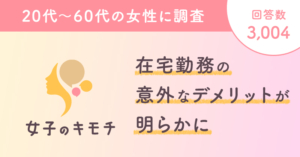アンケート調査の作り方~設計から成功の秘訣まで~
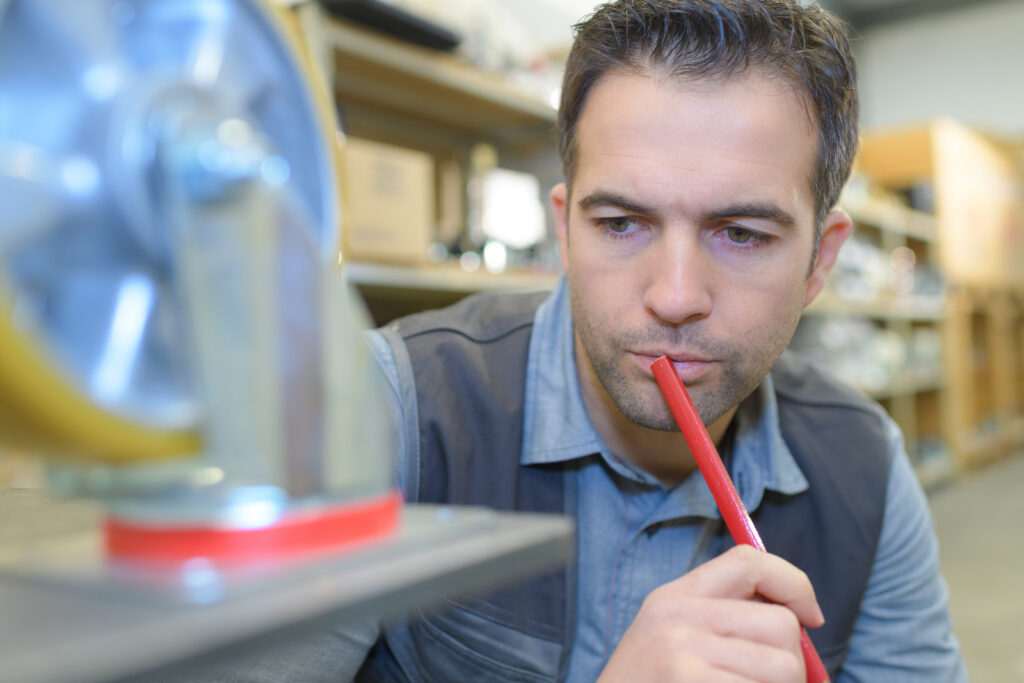
こんにちは。デジタルマーケティングカンパニーのトウガサです。
アンケート調査を成功させるためには、企画・設計から実施・分析に至るまで、一連の流れを適切に進めることが重要です。漠然とアンケートを実施するのではなく、目的を明確にし、適切な方法で情報を収集することが、ビジネスの意思決定やマーケティング戦略の評価に役立ちます。このガイドでは、効果的なアンケート調査の作り方と、成功に導くための具体的なノウハウを詳しく解説していきます。
アンケート作成の基本
アンケートを作成する際は、回答から得たい情報を明確にすることが基本です。目的を定めてから、適切な質問項目と回答形式を選び、スムーズな作成方法で進めることが重要となります。回答者がストレスなく回答できるような構成を意識しましょう。
アンケート作成の準備
アンケート作成の準備段階では、まず「何を調査したいのか」「何を知りたいのか」といった目的を明確に設定することが不可欠です。目的が曖昧なままでは、アンケートの方向性が定まらず、結果的に望むデータを得られない可能性があります。
調査の背景や目標、期待される結果とその活用方法まで具体的にまとめると良いでしょう。次に、アンケートの対象者を決定します。例えば、自社商品のユーザーを対象とする場合でも、性別、年齢、職業、既存顧客か見込み顧客かといった属性で細分化し、目的に合致したターゲット層に絞り込むことが重要です。
また、アンケートを実施する人数も事前に検討し、適切なサンプルサイズを選定します。これらの準備が整った後、具体的な質問項目をまとめた調査票の作成に移ります。無駄な質問を避け、必要な情報だけを効率よく収集できるよう、質問の選定と配置を慎重に行うことが求められます。この段階で、後に続く分析や意思決定に繋がる明確な調査票を作成することが、アンケート成功の鍵となります。

質問形式の種類
アンケートで利用される質問形式には、目的に応じて様々な種類があります。主に、単一回答、複数回答、自由記述、数値入力、マトリックス形式などがあります。例えば、顧客満足度を測る際には「非常に満足」「満足」「普通」「不満」「非常に不満」といった5段階評価の尺度を用いることが一般的です。
一方、商品の利用頻度などを尋ねる場合では、「毎日」「週に数回」「月に数回」「ほとんど利用しない」といった4段階評価が適していることもあります。これらの選択式の質問は、回答者が簡単に答えられるため、回答率の向上に繋がりやすいです。Webアンケートではドロップダウンリストの多用は回答者の負担になるため、避けるのが賢明とされています。
また、質問形式の選択は、回答者が考える負担を軽減し、思考停止で回答できるような設問にすることで、より多くの回答を集めることに繋がります。例えば、あらかじめ選択肢を用意しておくことで、回答者は事実の中から選ぶだけで済み、気軽にアンケートに答えやすくなります。適切な質問形式を選ぶことで、回答の精度を高め、効果的なデータ収集が可能になります。

アンケート項目の種類
アンケートを作成する上で、どのような項目を設定するかは非常に重要です。質問項目は、アンケートの目的に沿って慎重に決定する必要があります。例えば、顧客満足度調査を行う場合、単に満足度を問うだけでなく、商品やサービスのどの点に満足しているのか、あるいは不満を感じているのかといった理由を深掘りできる項目を盛り込むことが有効です。
具体的には、商品やサービスの利用頻度、利用開始時期、顧客が重視する点、改善してほしい点など、多角的な側面から情報を収集できる項目を設定します。また、回答者のデモグラフィック情報(年齢、性別、職業、居住地など)も重要な項目であり、これらの情報は回答の傾向を分析する際に役立ちます。ただし、質問の数を増やしすぎると回答者の負担となり、回答率の低下や回答の質の低下に繋がる可能性があるため注意が必要です。
目安として、アンケートは10分以内に回答できる設問数に収めることが推奨されており、もし質問数が多い場合は回答者のモチベーション維持のために謝礼の検討も必要になります。重要な項目に絞り込み、回答者が理解しやすく、かつ答えやすい形で質問を構成することで、より正確で有用なデータを収集することが可能になります。

効果的なアンケートの構成
効果的なアンケートの構成にはいくつかの注意点があります。例えば、回答を誘導するような質問や、複数の意味を持つ質問は避けるべきです。また、回答者の負担を考慮したフォーマットにすることで、回答率を高めることができます。
回答への影響を避ける工夫
アンケートの回答に影響を与える「誘導」質問を避けることは、客観的で正確なデータを収集するために非常に重要です。例えば、「この商品は大変人気がありますが、使用されていかがでしたか?」といった質問は、回答者に商品の人気度を事前に伝え、肯定的な回答を促す可能性があるため避けるべきです。
回答を誘導するような表現は、回答者の本来の意見を反映しない「バイアス(偏り)」を生み出す原因となります。質問文を作成する際は、中立的で客観的な言葉遣いを心がけ、特定の答えに誘導しないように注意しましょう。
また、質問の言葉遣いはシンプルで分かりやすく、専門用語の使用は避けるべきです。もし専門用語を使わざるを得ない場合は、短い定義や説明を加えることで誤解を防ぐことができます。質問の意図が曖昧であったり、複数の論点を含んでいたりする「多重質問」も避けるべき点です。
例えば、「このサービスは使いやすくて価格も妥当だと思いますか?」という質問は、使いやすさと価格の妥当性という2つの異なる要素を同時に尋ねており、回答者がどちらか一方にしか同意できない場合に適切な回答ができません。このような質問は分解して個別に尋ねる必要があります。
これらの工夫により、回答者は自身の意見を率直に表現しやすくなり、結果として信頼性の高いデータを収集できるようになります。

回答者の負担を考慮する
アンケート作成において、回答者の負担を軽減することは、回答率の向上と回答の質の維持に直結します。まず、アンケート全体の所要時間を短く設定することが重要であり、一般的には10分以内、理想的には3~5分程度で完了するような設問数に留めるのが望ましいです。設問数が多すぎると、回答者は途中で飽きてしまったり、回答を諦めてしまったりする可能性が高まります。
また、質問文はできるだけ簡潔で分かりやすい言葉遣いを心がけ、専門用語の使用を避けましょう。回答者が質問の意図をすぐに理解できるよう、曖昧な表現や回りくどい言い回しは避けるべきです。スマートフォンからの回答を考慮し、レイアウトやデザインもシンプルで読みやすいものにすることも重要です。複雑なマトリックス形式の質問や、スクロールが必要なドロップダウン形式は、特にスマホユーザーにとって負担となることがあります。
質問の順番も重要で、最初は年齢や性別といった答えやすい基本的な情報から始め、徐々に本題へと進む構成にすると、回答者はスムーズにアンケートに取り組めます。さらに、個人情報の記入を必須にせず、匿名での回答を可能にすることも、回答者の心理的なハードルを下げ、回答率を高める効果があります。これらの配慮により、回答者が最後までストレスなくアンケートに協力できるようになり、結果としてより多くの有用なデータを収集できる可能性が高まります。
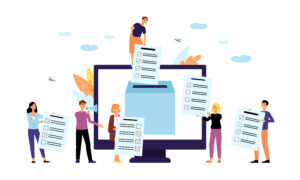
アンケート内容の最終確認
アンケート内容の最終確認は、実際に調査を開始する前の重要なステップです。このテスト回答の実施は、アンケートの品質を大きく左右します。
まず、作成したアンケートを自分自身で回答してみて、質問の流れが自然か、回答に迷う点はないかを確認します。
次に、可能であればターゲット層に近い複数の人にテスト回答を依頼し、率直なフィードバックをもらうと良いでしょう。これにより、客観的な視点からの問題点や改善点を発見できます。
特に確認すべき点としては、質問文が明確で理解しやすいか、専門用語が使われていないか、誤解を招く表現がないかといった点が挙げられます。
また、選択肢が網羅的かつ互いに排他的であるか、質問の意図が正しく伝わるかどうかも重要です。回答者がストレスなく回答できるような、設問の順番やデザインになっているかどうかも確認しましょう。例えば、マトリックス形式などの複雑な設問が多くないか、スマートフォンでの表示に問題がないかといった技術的な側面も考慮に入れる必要があります。
この最終確認を徹底することで、質問の意図が回答者に正しく伝わり、回答の質を高められるだけでなく、回収後のデータ分析がスムーズに進むようになります。

アンケート質問例とテンプレート

アンケートを作成する際に、ゼロから質問を考えるのは時間と労力がかかります。そこで、既存の質問例やテンプレートを活用することで、効率的にアンケートを作成し、質の高いデータを収集することが可能です。目的別に用意されたテンプレートや見本は、質問の構成や表現に迷ったときに大いに役立ちます。

アンケート作成ツールの紹介
アンケート作成ツールは、Webでアンケートフォームの作成から回答データの収集、集計までを効率的に行えるシステムです。これらのツールを活用することで、アンケート用紙の印刷や郵送にかかるコストを削減し、PCやスマホから手軽に回答できるため、回答者の負担を減らし回答率の向上にも繋がります。
また、回答データの自動集計機能や、結果のグラフ化機能が搭載されているものが多く、データ分析が容易になるというメリットもあります。テンプレートが豊富に用意されているツールもあり、アンケート作成の時間と手間を大幅に削減できるでしょう。
無料で利用できるツール
無料で利用できるアンケート作成ツールは、手軽にアンケート調査を始めたい場合に非常に役立ちます。代表的なツールとしては、Googleフォームが挙げられます。Googleフォームは、Googleアカウントがあれば誰でも無料で利用でき、直感的な操作でアンケートフォームを作成できるのが特徴です。
回答のリアルタイム集計や、Googleスプレッドシートとの連携機能も備わっており、データ管理や分析もスムーズに行えます。他にも、formrunやQuestant、CustomForm、SurveyMonkey、SELECTTYPEなども無料で利用できるプランを提供している場合があり、それぞれに特徴があります。
例えば、CustomFormは無料プランでも設問数や作成フォーム数に制限がないため、無料で何回もアンケート調査を実施したい場合に適しています。これらのネット上のツールは、アンケート用紙の印刷や郵送といった手間やコストを削減できるだけでなく、回答者がパソコンやスマホから手軽に回答できるため、回答率の向上にも繋がります。
無料ツールであっても、基本的なアンケート作成からデータ収集、簡単な分析までを行うには十分な機能を備えているため、まずはこれらのツールから試してみるのが良いでしょう。

専門的なアンケートツール
専門的なアンケートツールは、無料ツールでは対応しきれない複雑な調査や、より高度な分析を必要とする場合に非常に有用です。これらのツールは、単にアンケートフォームを作成するだけでなく、回答の分岐設定、多言語対応、詳細なデータ集計・分析機能、さらにはMAツールとの連携など、多岐にわたる機能を備えています。
例えば、formrunの有料プランは、テンプレートが豊富で、回答の自動集計やMAツールとの連携もできるため、データ分析や仮説検証にアンケートを利用したい企業にとって満足度が高いとされています。
また、Questantはアンケートに特化したサービスであり、質問タイプや選択肢のデータベースからの選択、質問の分岐やスキップの柔軟な設定、そして集計・分析機能の充実が特徴です。QiQUMOのようなセルフ型アンケートツールは、属性を活用してターゲットを絞り込み、低価格で多様な声を効率よく集められるなど、特定のニーズに特化した機能を提供しています。
これらのツールは、PマークやISMS認証などのセキュリティ対策も充実している場合が多く、企業の機密情報や顧客の個人情報を扱う際にも安心して利用できます。長期的に商用利用を検討している場合や、大規模な調査、あるいは複雑な分析が必要な場合は、これらの専門的なツールを導入することで、より精度の高いアンケート調査を実施し、ビジネスの成長に繋げることが期待できます。

アンケート実施の手順

アンケート調査の実施は、単に質問を作成するだけでなく、効果的な方法と手順を踏むことが重要です。適切な準備と計画を立てることで、効率的にデータを収集し、分析に繋げることが可能になります。Webアンケートだけでなく、郵送や対面といった様々な実施方法も存在します。
アンケート実施から集計まで
アンケートの実施から集計までの流れは、効率的なデータ収集と分析のために重要です。まず、作成したアンケートフォームを回答者に配布します。配布方法には、WebアンケートであればURLやQRコードの共有、自社ホームページやSNSでの募集、メールでの一斉送信などがあります。
インターネット調査は、多くの人に呼びかけができ、フォーム作成から結果のグラフ化までパソコン上で完結できるため、主催者側の負担も少ない方法です。紙媒体のアンケートであれば、郵送や対面での配布、イベント会場での設置などが考えられます。
郵送調査は回収率が低い傾向にあり、対面調査は時間はかかるものの、より精度の高いデータが得られる可能性があります。回答が集まったら、次にデータの集計を行います。Webアンケートツールを利用していれば、自動集計機能が搭載されていることが多く、リアルタイムで回答状況を確認し、結果をグラフ化することも可能です。
手動で集計する場合は、Excelなどにデータを入力し、グラフ作成機能などを活用して可視化することで、傾向や特徴を把握しやすくなります。集計後には、得られたデータを分析し、仮説の検証や新たな課題の発見に繋げます。この一連の作業を計画的に進めることで、アンケート調査の目的達成に貢献できます。

回答率を高める施策
アンケートの回答率を高めるための施策は、調査の成功に不可欠です。回答者に積極的に協力してもらうための方法は多岐にわたります。まず、アンケートの冒頭で目的や趣旨を明確に伝え、回答がどのように活用されるかを具体的に示すことが重要です。これにより、回答者は自身の回答が役立つと認識し、協力意識が高まります。
回答にかかる時間の目安を具体的に提示することも効果的で、例えば「5分程度で完了します」と伝えることで、回答者は心理的な負担を感じにくくなります。設問数をできるだけ少なくし、選択式を中心にするなど、回答者の負担を軽減する工夫も欠かせません。複雑な質問形式や長文の質問は避け、思考停止で回答できるようなシンプルさを心がけましょう。
また、回答者への謝礼やインセンティブを用意することも、回答率向上に非常に有効な方法です。金券やギフトカード、記念品、限定サービスなど、ターゲット層に魅力的な報酬を提供することで、回答へのモチベーションを高められます。匿名回答を許可することで、個人情報の取り扱いに関する懸念を払拭し、より本音に近い回答を引き出すことができます。
さらに、アンケートのタイトルを工夫したり、優先順位の高い質問を最初に配置したりするなどの設計上の配慮も、回答率向上に繋がります。これらの施策を組み合わせることで、回答者が快くアンケートに協力し、質の高いデータを収集できる可能性が高まります。

アンケート調査の種類と選び方
アンケート調査には、大きく分けて「定量調査」と「定性調査」の2種類があります。それぞれ異なる目的と手法を持ち、調査の目的に合わせて適切な種類を選ぶことが重要です。これらの調査を適切に使い分けることで、より深く、あるいは正確なマーケティングリサーチが可能になります。
定量調査の種類
定量調査とは、数値化できるデータを収集し、統計学的に分析する調査方法を指します。主に、全体的な傾向やパターンを把握し、仮説の検証や実態把握、効果測定を目的として実施されます。定量調査の主な種類には、以下のようなものが挙げられます。
まず、最も一般的なのがアンケート調査(ネットリサーチ)です。これは、インターネット上でアンケートフォームを配布し、多数の回答者からデータを集める方法で、短期間で多くの情報を収集できるメリットがあります。次に、会場調査(CLT:CentralLocationTest)とホームユーステスト(HUT:HomeUseTest)があります。
会場調査は、特定の場所に回答者を集め、そこで商品やサービスを体験してもらった上でアンケートに回答してもらう方法です。一方、ホームユーステストは、商品を自宅に持ち帰ってもらい、一定期間使用した後にアンケートで評価してもらう方法です。
これらは、新製品の評価や既存製品の改善点を探る際に用いられます。その他には、郵送調査や街頭調査、電話調査、FAX調査、来店者(来場者)調査などがあります。郵送調査は調査票を郵送し、回答者が返送する形式で、回収率は低い傾向にありますが、広範囲の対象者にアプローチできます。
街頭調査は、調査員が街頭で直接回答者に声をかけ、アンケートやインタビューを行う方法で、その場で即座に回答が得られるという特徴があります。定量調査は、客観的な数値データを得られるため、意思決定の根拠として説得力のある情報を提供できます。

定性調査の種類
定性調査とは、数値では測れない対象者の考えや心情、行動の背景など、深い情報を収集することを目的とした調査方法です。主に、仮説立案、行動理由や心理の深掘り、新たなアイデアの創出などに用いられます。定性調査の主な種類には、以下のような手法があります。
最も代表的なのがグループインタビュー(FGI:FocusGroupInterview)です。これは、3~8人程度の少人数グループを集め、特定のテーマについて自由に話し合ってもらう形式で、参加者同士の意見交換から新たな気づきを得られることがあります。
次に、デプスインタビュー(DI:DepthInterview)があります。これは、一対一で時間をかけて深く掘り下げたインタビューを行う方法で、個人の深層心理や複雑な感情、行動に至るまでのプロセスなどを詳細に把握するのに適しています。
その他には、家庭訪問(ホームビジット)や行動観察(エスノグラフィ、オブザベーション)、ワークショップ、MROC(MarketingResearchOnlineCommunities)などがあります。家庭訪問は、対象者の自宅を訪れて、実際の生活環境の中で行動や意見を観察する方法です。
行動観察は、特定の行動を直接観察することで、意識されていない行動や習慣を把握するのに役立ちます。
ワークショップは、参加者と共にアイデア出しや問題解決を行うことで、創造的な意見や解決策を引き出す手法です。定性調査は、数値では得られない「生の声」や「なぜそう思うのか」といった質的な情報を得るのに非常に有効ですが、調査やデータ集計に時間がかかり、数値として集計・管理するには向いていないという側面もあります。

調査種類の選択基準
アンケート調査の種類を選択する際には、調査の目的を明確にすることが最も重要な基準となります。定量調査と定性調査は、それぞれ異なる目的と得られる情報を持っているため、目的に合わせて適切に使い分ける必要があります。
例えば、「商品の利用状況や顧客満足度を数値で把握したい」「特定の仮説を多数の意見で検証したい」「全体的な傾向や市場の現状を把握したい」といった場合は、客観的な数値データが得られる定量調査が適しています。大規模なサンプル数を確保して調査することで、データの説得力が増し、意思決定の強力な根拠となります。
一方、「なぜ顧客がその商品を選ぶのか、どのような心理が働いているのかを深く知りたい」「新製品開発のためのアイデアを得たい」「顧客の具体的な不満点や改善点を詳細に洗い出したい」といった場合は、数値では測れない深い洞察や生の声を得られる定性調査が有効です。
定性調査は、対象者の行動理由や心理、感情などを深掘りするのに適しており、新たな仮説を立てる際にも役立ちます。より深く正確なマーケティングリサーチを目指す場合は、定量調査と定性調査を組み合わせて実施する方法も有効です。
例えば、まず定量調査で全体像を把握し、その結果から見えてきた課題や興味深い点について、さらに定性調査で深掘りするといった進め方があります。調査対象者の特性、調査にかけられる時間、予算なども考慮に入れ、最適な調査方法を選択することが、成功への鍵となります。

アンケート作成のポイント

アンケート作成の際には、いくつか重要な注意点があります。これらを意識して作成することで、回答の質を高め、信頼性の高いデータを収集できるようになります。質問の配置や内容、表現方法に至るまで、細部にわたる配慮が求められます。
回答数を増やす工夫
アンケートの回答数を増やすための工夫は、調査の成功に直結します。まず、アンケートの冒頭で趣旨を明確に伝え、回答にかかる時間の目安を具体的に提示することが重要です。これにより、回答者は安心してアンケートに取り組めます。
質問数を少なく抑え、複雑な質問形式や専門用語を避けるなど、回答者の負担を最小限にすることが基本です。質問は簡潔で分かりやすく、一問一答形式を心がけましょう。また、回答者への謝礼やインセンティブを用意することは、回答意欲を高める非常に効果的な方法です。金券やギフトカード、抽選でのプレゼントなど、ターゲット層に魅力的な報酬を設定しましょう。
Webアンケートの場合、回答フォームがスマートフォンなどあらゆるデバイスで快適に操作できるデザインにすることも重要です。ドロップダウン形式など、操作が増える要素はなるべく避け、選択肢形式にするなどの工夫で、回答者のストレスを軽減します。
さらに、アンケートの告知方法も重要です。自社サイトやSNS、メールマガジンなど、ターゲット層が普段利用しているサイトや媒体を通じて告知し、アンケートへのアクセスを促しましょう。回答期限を明記し、回答を促すリマインダーを送ることも有効です。これらの工夫を組み合わせることで、回答率の向上に繋がり、より多くの有効なデータを収集できるようになります。
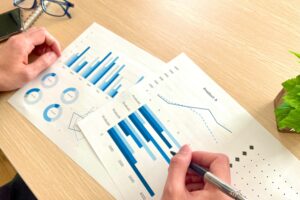
質問の配置順序
アンケートの質問の配置順序は、回答の質と回答率に大きく影響します。質問の順番を工夫することで、回答者の負担を軽減し、より正確な情報を引き出すことが可能です。一般的には、回答者が答えやすい質問から始め、徐々に本題やデリケートな内容へと進める「ウォーミングアップ」の形が推奨されます。
例えば、年齢や性別などの基本的なデモグラフィック情報や、サービス利用頻度といった客観的な質問を最初に配置することで、回答者はスムーズにアンケートに入り込めます。次に、興味や関心を探るモチベーションに関する質問、具体的な利用状況や満足度に関する質問(パフォーミング)、最後に個人情報やセンシティブな質問(クロージング)という4段階の順序が考えられます。
特に重要な質問は、回答者の集中力がある前半に配置すると良いでしょう。しかし、冒頭で核心をつくような質問をしてしまうと、回答者が警戒したり、先入観を植え付けたりする可能性があるため注意が必要です。また、前の質問が後の質問の回答に影響を与える「キャリーオーバー効果」にも留意し、質問項目間の因果関係を考慮して配置することが重要です。
例えば、特定の情報への認知度を問う質問の後に、それに対する意見を問う質問を配置することで、回答が偏る可能性を避けることができます。金額の選択肢は小さいものから大きいものへ、頻度の選択肢は頻度の高いものから低いものへといったように、選択肢の順序も論理的に配置することで、回答者は直感的に理解しやすくなり、精度の高い回答データを収集することに繋がります。これらの聞き方の工夫により、回答者はストレスなくアンケートに集中し、真の意見を述べやすくなるでしょう。

質問内容の統一性
アンケートの質問内容に統一性を持たせることは、回答の整合性を高め、データ分析の精度を向上させる上で不可欠です。まず、アンケート全体の目的と、個々の質問がその目的に合致しているかを常に意識することが重要です。
目的から逸脱した質問や、関連性の低い質問を盛り込むと、回答者の混乱を招くだけでなく、得られるデータも散漫になり、分析が困難になる可能性があります。各質問は、一貫したテーマや視点に基づいて作成し、論理的な流れを保つようにしましょう。
例えば、顧客満足度を測るアンケートであれば、「商品Aの満足度」について尋ねた後、別の質問で突然「商品Bの利用頻度」について尋ねるのではなく、商品Aに関する質問をまとめて配置するなど、関連性の高い質問をグループ化することが有効です。これにより、回答者は思考を切り替えることなくスムーズに回答を進められます。
また、質問文のトーンや表現方法も統一することで、回答者がアンケート全体を通して一貫した印象を持ち、質問の意図を正確に理解しやすくなります。例えば、敬語とタメ口が混在したり、専門用語と平易な言葉が入り混じったりすると、回答者に不信感を与えたり、混乱を招いたりする可能性があります。この統一性を保つことで、回答の偏りを防ぎ、信頼性の高いデータ収集に繋がります。

質問の明確化
アンケートの質問を明確にすることは、回答者が迷うことなく正確に回答するために最も重要なポイントの一つです。質問文が曖昧だと、回答者によって解釈が異なり、結果として信頼性の低いデータが得られてしまう可能性があります。例えば、「最近」や「いつも」、「多い・少ない」といった時間的表現や頻度の表現、量の表現は、人によって感覚が異なるため、具体的な期間や量を明記するなどして、誰にとっても同じ意味で捉えられるように明確化する必要があります。
また、一つの質問で複数のことを尋ねる「多重質問」は避けるべきです。例えば、「このサービスは使いやすく、機能も充実していると思いますか?」という質問は、「使いやすさ」と「機能の充実度」という二つの異なる要素を同時に尋ねているため、回答者がどちらか一方にしか同意できない場合に適切な回答が得られません。このような場合は、質問を分割してそれぞれを個別に尋ねるようにしましょう。
質問の意図が不明瞭であったり、回答を誘導するような表現になっていたりしないかどうかも確認が必要です。専門用語を使用する場合は、補足説明を加えるか、より平易な言葉に置き換えるなど、回答者の知識レベルに配慮した表現を心がけましょう。これらの点に注意し、質問文を簡潔かつ具体的に記述することで、回答者は迷うことなく、自身の意見を正確に反映した回答ができるようになり、結果として質の高いデータ収集に繋がります。

表現方法の注意点
アンケートの表現方法は、回答の質を大きく左右するため、細心の注意を払う必要があります。まず、質問文は中立的で客観的な言葉遣いを心がけ、特定の回答に誘導するような表現は避けるべきです。例えば、「健康のためにサプリメントは必要だと思いますか?」といった質問は、回答者にサプリメントの必要性を促す印象を与えかねません。
曖昧な言葉や専門用語の使用も避けるべき点です。「最近」「頻繁に」「多く」といった感覚的な表現は、人によって解釈が異なるため、具体的な期間や回数、量を明記するなど、誰にとっても同じ意味で理解できるような言葉に置き換えましょう。また、質問文はできる限り簡潔で短くまとめることが重要です。
長文や回りくどい表現は、回答者にストレスを与え、質問の意図を正確に伝えられない可能性があります。回答者が質問の意図をすぐに理解し、迷うことなく回答できるよう、シンプルな言い回しを心がけましょう。回答選択肢も、回答者が納得できる適切な表現になっているか確認が必要です。
選択肢は網羅的であり、かつ互いに排他的であることが理想的です。プライバシーに関わるようなセンシティブな質問は、表現に特に配慮し、必要であれば匿名回答を保証するなど、回答者が安心して答えられる環境を整えることも重要です。これらの表現方法に注意することで、回答者がストレスなく正直な意見を述べられるようになり、より信頼性の高いデータを収集することができます。
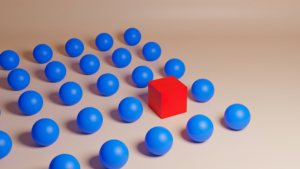
まとめとお問い合わせのご案内
アンケート調査は、設計から実施・分析に至るまでの一連の流れを丁寧に進めることで、信頼性の高いデータを得られ、マーケティング戦略や事業成長に直結する重要な取り組みです。
しかし「調査票の設計に自信がない」「自社に合った調査手法を知りたい」「分析までしっかりサポートしてほしい」といったお悩みを抱える企業も少なくありません。
株式会社オノフでは、企画設計・質問設計・対象者リクルーティング・集計分析・レポート作成まで、調査に関わる工程をワンストップでサポートしています。BtoB、BtoCを問わず豊富な実績をもとに、課題に合わせた最適なリサーチをご提案します。
「自社のマーケティングを次のステージへ進めたい」とお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。