アンケート調査の方法と種類を徹底解説|進め方・設計のコツも紹介

こんにちは。デジタルマーケティングカンパニーのトウガサです。
ビジネスパーソンやマーケティング担当者にとって、顧客や市場のニーズを把握することは不可欠です。本記事では、アンケート調査の方法、具体的な進め方、そして効果的な作り方まで、網羅的に解説します。アンケート調査を成功させ、ビジネスに役立つデータを得るためのヒントをお届けします。
アンケート調査の基礎知識
アンケート調査を実施する上で、その基本を理解することは非常に重要です。アンケートの調査方法には様々な種類があり、それぞれの特徴を把握することで、目的に応じた最適な調査計画を立てることが可能になります。まずはアンケート調査がどのようなものか、その基本的な概念と、調査手法の種類について掘り下げていきます。
アンケート調査とは
アンケート調査とは、特定のテーマに関する意見や情報を多数の対象者から効率的に収集し、その回答を分析することで、さまざまな課題解決に役立つ情報やデータを得るための調査方法です。企業においては、製品開発や顧客満足度向上、経営戦略策定などに広く活用されています。アンケートによって収集する情報は、数値化できる「定量的データ」と、言葉や行動といった数値化できない「定性的データ」の主に2つに分けられ、目的に応じて使い分けることが重要です。
回答者の意見や考えを直接尋ねることで得られるデータは「アスキングデータ」と呼ばれ、行動の背景にある動機やインサイトを深く探るのに役立ちます。また、POSデータやウェブサイトのアクセスログなど、実際の行動履歴から得られる「アクチュアルデータ」と組み合わせることで、「何が起こったか」と「なぜそれが起こったか」の両方を理解し、より精度の高いマーケティング戦略や意思決定が可能になります。

定量調査と定性調査の違い
アンケート調査の基本となる調査手法は、大きく「定量調査」と「定性調査」に分けられます。定量調査は、数値化できるデータを収集し、統計的な分析を行う調査手法であり、数百人以上の対象者に実施するのが一般的です。これにより、全体的な傾向や構造を把握できます。
例えば、「はい」「いいえ」で答えられる選択肢や、5段階評価といった質問項目によって、回答を数値として集計し、「全体の何%が同意しているか」といった数量的なデータを求める場合です。
一方、定性調査は、行動や感情、価値観など数値化できない「質的なデータ」を収集・分析することを目的としています。これは個人の意見や深層心理、行動の背景にある動機などを深く探る際に用いられ、インタビューやグループディスカッションなどが主な調査手法です。
定量調査は客観的で説得力のあるデータが得られるメリットがある一方で、定性調査は数値化できない消費者の心理を深く理解できるというメリットがあります。どちらの調査手法もマーケティングにおいて不可欠であり、目的に応じて使い分けたり、組み合わせて実施することが推奨されます。

市場調査とアンケート調査
市場調査は、マーケティングの観点から市場の動向を調査すること全般を指し、商品の需要や競合のシェア率などの現状を数値化・データ化してマーケティング活動に役立てる広範な研究です。一方、アンケート調査は、特定の対象者に対して質問を行い、その意見や行動を把握することを目的とした調査手法であり、市場調査で用いられる具体的な手段の一つです。
つまり、アンケート調査は市場調査の一部として位置づけられます。市場調査では、消費者のニーズや市場の動向を包括的に把握するために、アンケートだけでなく、POSデータ分析やアクセスログ解析などのアクチュアルデータと組み合わせることで、より多角的な調査内容となります。
アンケート調査で得られるアスキングデータは、
「なぜその商品を購入したのか」「どのような点に不満があるのか」といった行動の背景にある動機やインサイトを深く探るのに役立ち、アクチュアルデータと組み合わせることで
「何が起こったか」と「なぜそれが起こったか」の両方を理解し、より精度の高いマーケティング戦略や意思決定が可能となります。

アンケート調査の種類
アンケート調査には様々な調査手法と実施方法が存在しそれぞれ異なる特性を持っています目的に応じて適切な種類を選択することが精度の高いデータを収集し有効な示唆を得るために不可欠ですここではアンケートの回収方法と目的別の種類に焦点を当てて詳しく見ていきます
回収方法の種類
アンケート調査の回収方法には様々な種類があり、それぞれにメリットデメリットが存在します。インターネットが普及した現代では、Webアンケートが最も代表的なアンケート調査の方法となっています。ネット調査はWebサイト上での依頼、メールでの依頼、SNS上での実施などが挙げられ、低コストでスピーディに多くのデータを集められる点がメリットです。しかし、回答が集まりにくい場合や、ポイ活目的の回答によってデータの信頼性が損なわれる可能性もあるため、アンケートパネルの管理状況を確認することが重要です。
オフラインのアンケート調査の方法としては、紙のアンケート用紙を使用する郵送調査、特定の会場に集まってもらい試飲や試食などの評価を行う会場調査(CLT)、製品を試してもらいアンケートに回答してもらうホームユーステストなどがあります。郵送調査は回答者の都合の良いタイミングで回答できるため、質問量が多くても高い回収率が期待できますが、回答に時間がかかるというデメリットがあります。
また、ラジオや街頭でのアンケートはリアルな声を聞けるメリットがある一方で、調査員の聞き取り能力に左右されやすい点がデメリットです。これらのアンケート調査の方法は、目的に応じて単独で実施されたり、複数の方法を組み合わせてより効果的な調査を行うこともあります。

目的別の種類
アンケート調査は、その調査内容によって多岐にわたる種類が存在し、マーケティングにおける意思決定を支援するために、様々な目的で活用されます。
例えば、
自社の製品やサービスが市場でどの程度認知されているかを把握する「ブランド・認知度調査」は、新規事業の立ち上げ時やブランド戦略の見直しに有効です。
「顧客満足度調査(CS調査)」は、自社製品やサービスが顧客からどのように評価されているかを把握し、改善点やサービス品質の向上に役立てられます。
その他にも、顧客の使用実態を把握する「使用実態把握調査」、
消費者のライフスタイルや価値観を深く探る「ライフスタイル/価値観探索調査」、
競合他社の製品やサービスを分析する「競合調査」、
新しいアイデアやコンセプトの受け入れ可能性を評価する「コンセプトスクリーニング」、
市場を細分化しターゲット層を特定する「セグメンテーション調査」
など、様々な調査内容があります。
これらの調査は、集計されたデータを企業内で分析し、製品やサービスの課題解決や、マーケティング戦略の立案に活用されます。例えば、特定の製品に関する顧客の意見を短いアンケートで収集し、クイックに評価をテストするといった活用も考えられます。目的を明確にすることで、最適なアンケート調査の方法と質問項目を選択し、より有効なデータを得ることが可能となります。
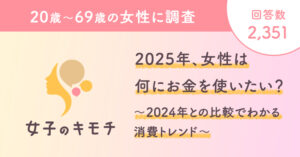
アンケート調査の進め方

アンケート調査は、質問を作成して回答を集めるだけでなく、効果的なデータを得るための明確な進め方があります。計画から準備、質問票の作成、実施、そしてデータ分析までの一連のプロセスを適切に管理することが重要です。ここでは、アンケート調査をスムーズに進めるための各ステップを詳しく解説します。
計画と準備
アンケート調査を始める上で最も重要なのは、具体的な計画と事前の準備です。まず、「何を明らかにしたいのか」という目的を明確に設定することが不可欠です。目的が曖昧なままでは、アンケート調査の方法や質問内容が定まらず、有効なデータを得ることができません。
例えば、顧客満足度の向上を目指すのであれば、具体的な不満点や改善点を明確にする必要があります。
次に、誰から情報を得たいのかという「ターゲット」を明確に設定します。
例えば、新規顧客と既存顧客、または特定の年齢層や職業のビジネスパーソンなど、調査目的に合わせて対象者を絞り込むことで、より質の高い回答を得られます。この段階で、アンケート調査によってどのようなデータが得られれば、意思決定に役立つのか、期待される結果と活用方法まで具体的に想定しておくことが、その後のプロセスをスムーズに進める上で不可欠です。
また、回答者を特定の方向に誘導するような質問の仕方を避けるよう、質問内容の方向性もここで検討します。

質問票の作成
アンケート調査の質問票は、回答者から必要な情報を正確に収集するための羅針盤のような存在です。質問票の作り方一つで、得られるデータの質は大きく左右されます。まず、調査の目的に沿った質問を設定し、回答者が答えやすいように工夫することが重要です。質問は簡潔で明確にし、専門用語の使用は避けるべきですが、対象者が専門家である場合は適切に使用することもあります。
回答形式は、自由記述よりも選択肢を設定する方が、後々の集計や分析が容易になります。例えば、5段階評価のような段階的な選択肢を用いることで、回答者の微妙なニュアンスを捉えることが可能です。
また、質問の順番も重要で、回答者が自然に答えられるような論理的な流れを意識しましょう。
例えば、知っているかどうか、購入したことがあるか、その評価はどうか、そして購入意向という流れが自然です。
設問数は、一般的に20問前後が理想的とされており、回答者のモチベーション維持のため、10分以内に回答できるボリュームに抑えるのが望ましいです。回答しづらい質問や誘導的な表現は避け、中立的な表現を心がけましょう。質問票作成に役立つテンプレートや例文を活用することで、効率的に質の高い質問票を作成できます。

調査の実施と回答収集
アンケート調査の計画と質問票の作成が完了したら、いよいよ調査の実施と回答の収集に移ります。アンケート調査の方法によって実施期間や回収方法が異なるため、事前に集計方法や回答の収集方法を決めておくことで、スムーズな進行が可能です。オンラインでアンケートを実施する場合は、Webアンケートフォーム作成ツールやネットリサーチツールを活用すると、効率的に回答を集められます。
自社のWebサイトやSNSでアンケートを告知し、回答を募ることも有効な方法です。一方、オフラインでのアンケート調査では、郵送調査や街頭調査、会場調査(CLT)などがあり、それぞれの特性を理解して選択することが重要です。
郵送調査では回答者が都合の良いタイミングで回答できる反面、回収に時間がかかる可能性があります。街頭調査ではリアルな声を聞けるものの、調査員の能力に左右されることがあります。回答収集においては、回答率を高めるための工夫も重要です。
例えば、回答完了までにかかる目安時間を提示したり、回答者への謝礼を用意したりすることで、回答意欲を高めることができます。収集したデータは、後に分析しやすいように適切に管理することが求められます。

データ分析と結果のまとめ
アンケート調査で収集した回答データは、その後の施策立案や意思決定に活用するために、適切に分析し、結果をまとめることが非常に重要です。データの集計方法としては、まず各質問項目の回答割合を算出する「単純集計」を行い、全体の傾向を把握します。
次に、複数の質問項目を組み合わせて集計する「クロス集計」を実施し、変数間の関連性や、性別・年代などの属性ごとの特徴を分析します。これにより、例えば「女性の20代は〇〇という商品に高い関心を持っている」といった具体的な傾向を把握することができます。集計されたデータは、仮説検定や回帰分析、因子分析といった統計的な手法を用いてさらに深く分析されることもあります。
分析の結果は、レポートやプレゼンテーション資料にまとめられ、調査依頼者に報告されます。この際、単に数値を羅列するだけでなく、分析から得られた知見や、それがマーケティング施策の立案や製品開発、顧客満足度向上にどのように活用できるかを明確に伝えることが、調査の成果を最大化する上で不可欠です。分析結果を適切に解釈し、次のアクションへとつなげる洞察を引き出すことが、アンケート調査の最終的な成功を左右します。

アンケート調査を成功させるコツ

アンケート調査を成功させるためには、質問の作り方から回収率の向上、適切なツールの活用まで、多角的な視点からの工夫が求められます。ここでは、アンケート調査の方法論を実践し、質の高いデータを効率的に得るための具体的なコツを解説します。
回答率を高めるための工夫
アンケート調査を成功させる上で、回答率を高めることは非常に重要です。回答率が低いと、想定したサンプルサイズを確保することが難しくなり、調査結果の信頼性が損なわれる可能性があります。
回答率を高めるための工夫としては、まずアンケートの趣旨や目的を冒頭で明確に伝え、回答者が「なぜこのアンケートに協力するのか」という意義を理解できるようにすることが大切です。
また、回答者の負担を軽減するために、設問数を少なくし、回答にかかる目安時間を提示することが推奨されます。一般的に、アンケートは選択式の質問を中心とすることで、回答者の心理的なハードルを下げられます。自由記述の項目は、重要な部分に絞って設けるようにしましょう。
さらに、回答者への感謝の気持ちとして、謝礼やインセンティブを用意することも効果的です。インセンティブは、回答者の属性や嗜好に合わせて選定し、アンケートの種類や回答方法に見合った価値のあるものにすることが、回答意欲を高める誘導になります。質問の順序も重要で、興味を引く質問から開始し、関連性の高い質問をまとめて配置するなど、回答しやすい論理的な流れにすることで、回答者の途中離脱を防ぎ、回答率の向上に繋がります。
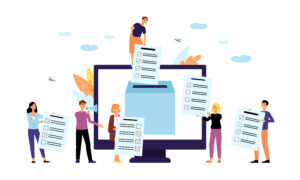
アンケート作成に役立つツール
アンケート調査を効率的に実施し、質の高いデータを得るためには、適切なツールの活用が不可欠です。Webアンケートフォーム作成ツールは、アンケートの作り方を簡素化し、配布から回答収集、そしてデータ集計までをWeb上で完結できるため、多くのビジネスパーソンに利用されています。
Googleフォームは、無料で利用でき、質問形式のカスタムからリアルタイム集計、Googleスプレッドシートとの連携まで可能なため、手軽にアンケートフォームを作成したい場合に適しています。質問数は100個まで、回答数は1万個まで無料で利用できますが、収容量は100MBまでという制限があります。
SurveyMonkeyも、専門家が作成したテンプレートが豊富に用意されており、AIを活用して手軽にアンケートを作成できるツールとして人気があります。無料プランでは、アンケートの作成と送信は可能ですが、質問数が10個まで、1つのアンケートにつき表示できる回答数が40件までという制限があります。
formrunは、無料プランでフォーム作成数が1つまで、回答データダウンロードは直近1日のみなどの制限があるものの、ドラッグ&ドロップで簡単にフォームを作成できます。 2024年5月7日より、無料プランでも条件分岐機能が利用できるようになりました。
SELECTTYPEは、無料プランでも豊富なテンプレートを利用でき、簡単に予約画面を作成できますが、広告が表示されるほか、予約受付期間が7日後までという制限があります。
CustomFormは、無料プランで条件分岐や回答データのダウンロード機能が利用可能で、フォーム作成数や回答数に制限がない点が魅力です。 ただし、無料プランでは回答完了ページや集計結果ページに広告が表示されます。
これらのツールは、無料プランでも小規模なアンケートであれば十分活用できますが、設問数や作成フォーム数、回答収集数に制限がある場合があります。 有料プランでは、さらに高度な分析機能やセキュリティ対策、自動返信メールの設定などが利用可能です。 自社で回答を集めるのが難しい場合や、より専門的な市場調査を行いたい場合は、リサーチ会社が保有する調査モニターを対象にアンケートを依頼できるネットリサーチツールも有効な選択肢となります。

まとめ|調査設計から施策実装まで、オノフが伴走します
本記事で紹介した「目的設計 → 質問票作成 → 回収 → 集計・分析 → 施策化」の一連の流れは、現場での実行力が要です。 株式会社オノフでは、定量・定性の調査設計、母集団/サンプリング、質問票のバイアス対策、CLT・HUT・Web回収、品質管理(重複/不正除外)、可視化ダッシュボード、NPS/CSAT等の分析、そしてUI/UX・CRM・コンテンツまでの改善実装までをワンストップで支援します。
生活者パネル「みんなのプロジェクト」を活用した迅速な回収も可能です。
調査の立ち上げや見直しをご検討中の方は、まずは課題とゴールをお聞かせください。
株式会社オノフへお気軽にご相談ください!
