Webアンケート調査の基本|調査の種類と依頼方法をわかりやすく紹介

Webアンケート調査は、インターネットを活用して効率的に多くの意見を収集できる手法です。
この記事では、Webアンケート調査の基本的な知識から、具体的なメリット、目的別の種類、実施手順、さらには依頼先の選び方までを網羅的に解説します。
初めて調査を担当する方でも、一連の流れと重要なポイントを理解できるよう、わかりやすく説明していきます。
Webアンケート調査とは?その概要と特徴を解説
Webアンケート調査とは、インターネットを利用してweb上でアンケートを実施し、回答を収集するリサーチ手法です。
従来の郵送や訪問による調査と比較して、場所や時間の制約を受けずに広範囲の対象者から効率的に情報を集められる点が大きな特徴です。
回答データは自動的にデジタル化されるため、集計や分析作業の手間を大幅に削減できる利便性も備えています。
Webアンケート調査が選ばれる3つのメリット
Webアンケート調査が多くの企業で採用される背景には、明確なメリットが存在します。
主な利点として、コストと時間の削減、広範囲からの迅速な回答収集、そしてデータ集計の自動化が挙げられます。
これらのメリットは、市場の動向をスピーディーに把握し、迅速な意思決定が求められる現代のビジネス環境において、非常に有効な手段となり得ます。
メリット1:調査にかかる費用や時間を大幅に削減できる
Webアンケート調査は、従来の調査方法に比べて費用と時間を大幅に抑制できます。
紙の調査票の印刷費や郵送費、会場費、調査員の配置にかかる人件費などが不要になるため、コストを大きく削減可能です。
また、アンケートの配信から回答の回収までをweb上で行えるため、調査期間を短縮できます。
近年では、無料で利用できるフリーのアンケート作成ツールも数多く提供されており、低予算でも手軽に調査を始められる環境が整っています。

メリット2:遠隔地の対象者からもスピーディーに回答を集められる
インターネットを介して実施するため、地理的な制約がなく、全国各地や海外といった遠隔地の対象者にも一斉にアプローチできます。
回答者はパソコンやスマートフォンさえあれば、時間や場所を選ばずに都合の良いタイミングで回答できるため、短期間で多くのサンプルを効率的に集められます。
自動で回答を催促するリマインドメールの送信機能などを活用することで、回答率の向上も図りやすく、スピーディーな調査進行を実現します。
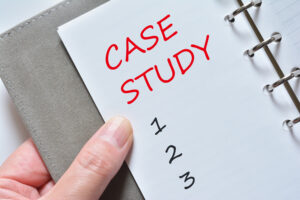
メリット3:回答データの集計やグラフ化を自動で行える
回答データが直接システム上に蓄積されるため、紙の調査票をデータ化する入力作業が不要です。
これにより、手作業による入力ミスを防ぎ、正確なデータを迅速に得られます。
多くのアンケートシステムには、回答結果をリアルタイムで自動集計する機能や、円グラフや棒グラフなどに変換する機能が標準で搭載されています。
集計作業にかかる時間と労力を削減できる分、本来の目的であるデータの分析や考察に多くの時間を充てることが可能になります。

【目的別】Webアンケート調査の代表的な2つの種類

Webアンケート調査は、誰を対象にアンケートを実施するかによって、大きく2つの種類に分類されます。
一つは、調査会社が保有するアンケートモニターを対象とする「モニター調査」です。もう一つは、自社のウェブサイト訪問者や顧客リストなどを対象とする「オープン調査」です。
どちらの手法を選択するかは、調査の目的やターゲット層、予算などによって異なり、それぞれの特性を理解した上で使い分ける必要があります。
モニター調査:調査会社のパネルを対象に実施する
モニター調査とは、調査会社が事前に募集・管理しているアンケート協力者(モニターパネル)に対してアンケートを配信する手法です。
モニターは性別、年齢、居住地、職業といった属性情報があらかじめ登録されているため、調査したいターゲット層の条件に合致する対象者を絞り込んで、効率的に意見を収集できます。
市場全体の動向や特定セグメントのニーズを探る市場調査、商品やサービスの認知度調査など、広く一般の消費者を対象とする場合に適しています。
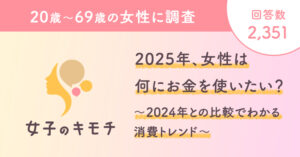
オープン調査:自社サイトの訪問者などを対象に実施する
オープン調査は、自社のwebサイトやメールマガジン、SNSなどを通じてアンケートへの協力を呼びかける手法です。webサイト上にアンケートフォームのhtmlを埋め込んだり、URLを告知したりして回答を募ります。
この方法の利点は、自社の商品やサービスに既に関心を持っている層から直接、意見や感想を収集できる点にあります。そのため、顧客満足度調査や、自社webサイトの利便性向上を目的とした調査などで有効に活用されます。モニター調査に比べ、費用を抑えて実施できるケースが多いです。

Webアンケート調査の進め方【4つのステップ】
Webアンケート調査を成功させるためには、計画的に手順を踏んで進めることが重要です。
まずは調査の目的を明確化する企画設計から始まり、次に回答者の視点に立った調査票を作成します。
その後、作成したアンケートを対象者に配信して回答を回収し、最後に集まったデータを集計・分析してレポートにまとめる、という4つのステップで進行します。
この一連の流れを理解することで、スムーズな調査実施が可能となります。
STEP1:調査の目的を明確にし企画を設計する
最初に「この調査で何を知りたいのか」「結果を何に役立てるのか」という目的を具体的に設定します。
目的が明確であれば、調査対象者(誰に聞くか)、必要な回答者数、聴取すべき調査項目(何を聞くか)といった調査全体の骨格が定まります。
例えば、「新商品の購入意向を探る」という目的であれば、ターゲット層に対してコンセプトの魅力度や価格の妥当性といった項目を尋ねる企画が考えられます。
この企画設計が、調査の成否を分ける最も重要な工程です。
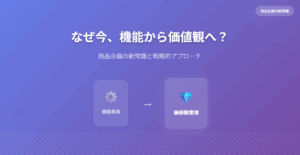
STEP2:回答者の負担を考慮した調査票を作成する
調査票は、回答者がストレスなく最後まで回答できるよう配慮して作成する必要があります。
設問数が多すぎたり、専門用語が使われていたりすると、回答の途中で離脱される原因となります。
設問の表現は誰にでも分かりやすい平易な言葉を選び、回答の流れが自然になるように順序を工夫します。
多くのアンケートツールには、設問のテンプレートが用意されているため、それらを参考にしながら自社の目的に合わせてカスタマイズすると、効率的に質の高い調査票を作成できます。

STEP3:アンケートを配信して回答を回収する
完成した調査票を対象者に届け、回答を収集する段階です。
モニター調査であれば調査会社が配信を行いますが、オープン調査の場合は自社のメールマガジンやWebサイト、SNSなどを活用して告知します。
専用のアンケートツールやシステムを利用すると、配信対象者の管理や回答状況のリアルタイムでの把握が容易になります。
あらかじめ設定した回答期間内に目標のサンプル数に達しない場合は、リマインドメールを送るなどの対策を講じることも有効です。

STEP4:集計結果をグラフ化しレポートにまとめる
回収した回答データを集計・分析し、調査結果を報告書としてまとめる最終ステップです。
多くのWebアンケートツールでは、単純集計やクロス集計といった基本的な集計が自動で行え、結果をグラフで視覚化できます。
例えば、「webcas」などの高機能なシステムでは、レポート作成を支援する機能も備わっています。
データから読み取れる事実や傾向を分析し、考察を加えてレポートを作成することで、調査企画時に設定した課題に対する示唆を得られます。
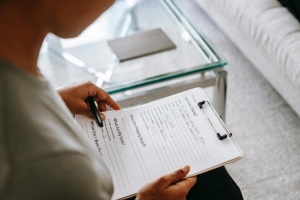
Webアンケート調査を依頼する2つの方法

Webアンケート調査を実施する際には、自社のリソースや調査の目的に応じて依頼方法を選択できます。
一つは、調査の専門知識を持つリサーチ会社に、企画から分析まで全ての工程を委託する方法です。
もう一つは、アンケートシステムやツールを導入し、調査の企画から実施、分析までを自社内で行う方法です。
それぞれにメリットとデメリットがあるため、自社の状況に合った方法を見極めることが求められます。
専門の調査会社に企画から分析まで一括で依頼する
専門の調査会社に依頼すると、リサーチのプロフェッショナルが企画設計から調査票の作成、集計、分析レポートの作成までを一貫して担当してくれます。社内に調査のノウハウやリソースがない場合でも、質の高い調査を実施できるのが最大の利点です。
また、調査会社が抱える豊富なモニターを活用できるため、特定の条件に合致する対象者からの回答を効率的に集められます。ただし、アンケートシステムを自社で利用する場合に比べ、費用は高くなる傾向があります。
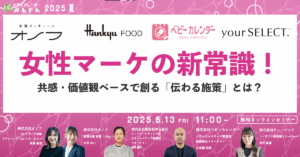
アンケートシステムを導入して自社で運用する
アンケートシステムを導入して自社で調査を行う方法は、調査会社に都度依頼するよりも費用を抑えられる点が魅力です。
月額制のサービスも多く、一度契約すれば好きなタイミングで何度でもアンケートを実施できるため、顧客満足度調査やイベント後の感想アンケートなど、定常的に調査を行いたい場合に適しています。
ただし、調査の企画や設問の作成、結果の分析は自社で行う必要があるため、一定の知識や工数が求められます。操作が簡単なツールも多いため、初心者でも比較的容易に始められます。

依頼先やツールを選ぶ際に確認したい3つの比較ポイント
自社に最適な調査会社やアンケートツールを選ぶためには、いくつかの重要なポイントを比較検討する必要があります。
特に、「料金体系」「サポート体制」「セキュリティ対策」の3点は、事前に必ず確認すべき項目です。
これらのポイントを基準に複数のサービスを比較することで、コストパフォーマンスが高く、安心して利用できる依頼先を見つけ出すことが可能となり、導入後のミスマッチを防ぎます。
料金体系は調査の規模や頻度に見合っているか
料金体系はサービスごとに異なり、初期費用や月額固定費、回答数に応じた従量課金など多岐にわたります。年に数回程度の利用であれば、実施する都度支払いが発生するプランが適しているかもしれません。
一方で、頻繁に調査を行う場合は、月額固定で使い放題のプランの方がコストを抑えられる可能性があります。
自社が想定する調査の規模や頻度を考慮し、最も費用対効果の高い料金体系のサービスを選択することが重要です。無料トライアルがあれば、積極的に活用して機能や使い勝手を比較検討しましょう。

初めてでも安心できるサポート体制が整っているか
特にWebアンケート調査の実施が初めての場合、サポート体制の充実は非常に重要な比較ポイントです。
操作方法で不明な点が生じた際や、万が一のトラブル発生時に、電話やメールなどで迅速に対応してくれる窓口があるかを確認しましょう。
また、FAQやオンラインマニュアルが整備されているかもチェックすると良いです。
導入実績が400社を超えるような信頼性の高いサービスの中には、調査票の作成方法についてアドバイスをもらえるなど、手厚いサポートを提供している場合もあります。
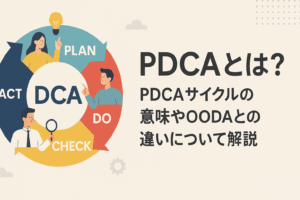
個人情報を守るためのセキュリティ対策は万全か
アンケートでは、回答者の氏名や連絡先といった個人情報、あるいは企業の機密情報に関わる内容を扱う可能性があります。
そのため、依頼先やツールが信頼できるセキュリティ対策を講じているかは、必ず確認しなければならない項目です。
具体的には、通信が暗号化されているか(SSL/TLS対応)、不正アクセスを防ぐ仕組みが導入されているか、そしてプライバシーマークやISMS認証といった第三者認証を取得しているかなどが判断基準となります。
情報漏洩は企業の信用を大きく損なうため、万全の対策が施されているかを見極める必要があります。

Webアンケート調査で気をつけるべき2つの注意点

手軽で便利なWebアンケート調査ですが、その特性に起因する注意点も存在します。
調査結果の信頼性を高めるためには、これらの注意点をあらかじめ理解し、対策を講じることが不可欠です。
特に、回答者がインターネット利用者に限定されることによる偏りの可能性や、多様なデバイスからの回答を想定した設計の必要性は、企画段階から念頭に置いておくべき重要なポイントです。
回答者がインターネット利用者に偏る点を理解しておく
Webアンケート調査は、インターネットを利用している人でなければ回答できません。
そのため、調査結果はインターネットユーザーの意見に偏るという特性があります。
例えば、インターネットの利用率が比較的低い高齢者層などを調査対象とする場合、Webアンケートだけではその層の意見を十分に集めることが難しい可能性があります。調査対象によっては、モバイルウェブの利用状況も考慮し、郵送調査や電話調査といった他の手法と組み合わせて、回答者の偏りを補う工夫が求められることもあります。
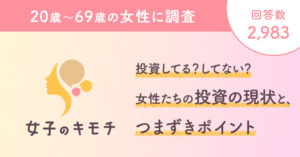
PCとスマホ両方からの回答を想定した設計にする
現在では、スマートフォンからインターネットにアクセスする人が多数を占めており、アンケートもスマートフォンで回答されるケースが非常に多くなっています。
そのため、アンケートフォームはPCとスマートフォンの両方の画面で、見やすく、回答しやすいように設計することが不可欠です。
PC画面でしか表示を確認しないと、スマートフォンでは文字が小さすぎたり、選択肢がタップしにくかったりして、回答者の途中離脱を招く原因になりかねません。
必ず両方のデバイスで表示確認を行い、誰にとっても回答しやすいデザインを心掛けるべきです。

まとめ
Webアンケート調査は、コストと時間を抑えつつ、広範な対象者から意見を収集できる効率的なマーケティングリサーチの方法です。調査の成功は、目的の明確化、回答者に配慮した調査票の作成、そして自社の状況に適した実施方法やツールの選択にかかっています。
モニター調査やオープン調査といった種類の特徴を理解し、企画から分析までの各ステップを丁寧に進めることが重要です。また、回答者の偏りやマルチデバイス対応といった注意点も踏まえることで、より精度の高い調査結果を得ることが可能になります。
Webアンケート調査は、目的に合わせた設計と適切な方法選びが成功の鍵となります。
もし「自社に合った調査方法が分からない」「アンケート設計から分析まで支援してほしい」といったご要望がございましたら、株式会社オノフにご相談ください。リサーチの専門チームが、企画から実施・分析・改善提案までを一貫してサポートいたします。
